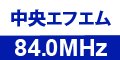『東海道四谷怪談』で知られる"お岩さん"の伝承を受け継ぐのが新川にある田宮於岩稲荷神社(写真上左右)である。もともとは怪談とか怨霊とかでお岩稲荷が祀られたのではなかった。
 同社の由来によると四谷左門町に住む田宮家のお岩と伊左衛門夫婦は薄給で苦しい生活を送っていた。そのため奉公に出たり、日ごろから屋敷社を信仰したおかげで蓄財も増えたという。お岩は寛永13年(1636)、36歳で亡くなった。そこで「お岩稲荷」の祠を造って人々に参詣が出来るようにした。享保2年(1717)「お岩稲荷」を勧進し「於岩稲荷社」となった。それからは「四谷稲荷」「左門町稲荷」とも呼ばれ、開運や災難除けとして江戸の人気を得るようになったそうだ。
同社の由来によると四谷左門町に住む田宮家のお岩と伊左衛門夫婦は薄給で苦しい生活を送っていた。そのため奉公に出たり、日ごろから屋敷社を信仰したおかげで蓄財も増えたという。お岩は寛永13年(1636)、36歳で亡くなった。そこで「お岩稲荷」の祠を造って人々に参詣が出来るようにした。享保2年(1717)「お岩稲荷」を勧進し「於岩稲荷社」となった。それからは「四谷稲荷」「左門町稲荷」とも呼ばれ、開運や災難除けとして江戸の人気を得るようになったそうだ。
お岩死去から189年後の文政8年(1825)になって、4世鶴屋南北作『東海道四谷怪談』が中村座で初演された。配役は「岩」に3代目尾上菊五郎、「伊右衛門」を7代目市川団十郎が演じたという。実はこの作品のもとになったのは、『四谷雑談集』に載っていたものであったそうだ。元禄時代に起こった事件の噂話などを怪談として創作されたものであるといわれている。
作者の4世鶴屋南北は宝暦5年(1755)日本橋新乗物町(現日本橋堀留)で生まれた。父は紺屋の型付職人であったが狂言作家としての道を選び、文化8年(1811)に4世を襲名した。『東海道四谷怪談』をはじめ傑作を残したので、「大南北」と称された。文政12年(1829)深川の黒船稲荷地内の居宅で死去した。享年75歳。現在江東区牡丹の同稲荷社には説明板が設置されている(写真下右)。
新川の田宮於岩稲荷神社は、役者の市川左団次から「四谷は遠すぎるので、新富座のそばに移転してほしい」と要望があり、四谷左門町の社殿が明治12年(1879)火災で焼失したのを機会に現在地に移転した。境内の石造鳥居は明治30年(1897)造立のもの、また百度石は区内現存最古のもので、ともに