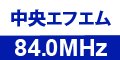日本橋兜町に「中央区立阪本小学校」(写真上)がある。明治6年(1873)創立の第1大学区第1中学区第1番学校なので、通称「一、一、一学校」として歴史は古く、また谷崎潤一郎出身校でも知られている。そのとなりは明治22年(1889)開園の「区立坂本町公園」(写真中)である。お気づきのように、ここに「阪本」と「坂本」、2種の表記がある。
 「坂本町」の名は近江国比叡山延暦寺の守護神、日吉大社の門前町である「坂本」に倣って、という。江戸末期の絵図では山王御旅所(日枝神社)門前の西側に所在し、俗称植木店(たな)とも呼ばれた。町名の名残は茅場町薬師、現在の智泉院境内に天保12年(1841)奉納の天水鉢(区民文化財=写真下)があり、「坂本町」と記されている。
「坂本町」の名は近江国比叡山延暦寺の守護神、日吉大社の門前町である「坂本」に倣って、という。江戸末期の絵図では山王御旅所(日枝神社)門前の西側に所在し、俗称植木店(たな)とも呼ばれた。町名の名残は茅場町薬師、現在の智泉院境内に天保12年(1841)奉納の天水鉢(区民文化財=写真下)があり、「坂本町」と記されている。
「坂本町公園」は江戸期からの歴史的地名を踏襲しているが、それでは「阪本」とは、どうしてなのだろうか。
ご承知のとおり、同じような例がある。江戸期は「大坂」であったものが、今は「大阪」。伊勢国「松坂」は、三重県「松阪」(地名の正しい読みは「まつさか」で、濁らない)と表記する。
こんな俗説がある。
1. 「坂」は傾き、転げ落ちるので不吉だから、よって「阪」に変えたとか。
2. 「坂」には「土に返る」ということで「消滅」につながり縁起が悪いので、「丘・大きい・多い・豊か・盛ん」の意味を表す「阜(フ)」をもとにした「こざとへん」の「阪」が当てられたとか。
3. 「坂」は「士が反く(武士が叛く)」から、「阪」にした。
――など。
「坂=縁起が悪い」が共通項のようであるが、作り話か否か、真偽のほどは分からない。詳しくご存知の方は教えていただきたい。明治期以降「阪」が使われていったようだ。いずれにしろ、この地は「坂」と「阪」が対比できる場所である。
ちなみに「坂」は常用漢字で、小学3年生で習う学習漢字である。しかし、「阪」は常用漢字にはなく、「坂」の異体字とされるが、現在見直し中の常用漢字追加候補には入っているので、「阪本」も「大阪」もようやく大手を振れそうだ。