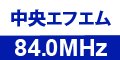[kimitaku]
2012年7月10日 13:00
7月8日午前7時半 小雨降るなか、住吉神社社殿でお祓いを受け、 来月3日からの大祭に向けての作業開始。
昨年は延期になり、4年ぶりの祭りです。



お神酒を神主さんから授かり」、皆さんそれぞれ持ち場に移ります。
この堀の水中に大幟の柱6本と、抱き木が埋まっています。
これを掘り出すのは潮が引いてからとのこと、
まずは 黒木鳥居の建立。
境内から。 巨大な檜材を境内から運びます。 それに二本の柱を組み合わせ、鳥居をつくり、クレーンで吊ります。
360年間この作業形態は、クレーン以外はほとんど昔のまま、江戸時代と変わりません。職人さんは頼まず、すべての作を講中で行います。
慣れない手付きの人も、初めての人も、熟練者の指導で皆さんが一つになって働く姿は一見の価値。 ・・・・・・・・さすが、江戸っ子(先祖は大阪)、佃の粋の良さ。・・・・・



最後に、クレーンで吊り上げ、立てかけます。



よそでは、柱の穴掘り、櫓建て、そして、水中にある、幟柱、抱き木
掘り出しのための砂堀、それぞれ皆さんが、持ち場で、懸命に働いています。



 佃堀での作業は、潮時を見て、潮待ちをして、行われます。
佃堀での作業は、潮時を見て、潮待ちをして、行われます。
午後の柱掘り出し作業は正午から、潮が引いて掘り出しやすくなってから行われました。
佃堀での、砂堀り、土嚢積み、皆さん、泥まみれで大変。 潮は次第に引いて行きます。
海に縁のある、佃の祭り.
長老の「おーい・・・・・」の声に素直に反応。 でもみなさんとても楽しそうでした。
次は、大幟柱建立 7月下旬です。

・・・・ところで この建立された、鳥居の、右の柱のほぞ木が少し欠けています。
これは、外側と内側を間違えて打ち込み、もう一度やり直した際にできたものです。
・・・・・・・・・・・・・・・・いわゆる、 刀傷・・・・・・・・・
[ジミニー☆クリケット]
2012年7月 9日 18:43
ヨハネス・フェルメール《真珠の耳飾りの少女》

6月30日から、上野の東京都美術館で、「マウリッツハイス美術館展 オランダ・フランドル絵画の至宝」が開催され、フェルメールはじめフランドル画家たちの作品をじかに鑑賞できますが、銀座でも、今年の1月から、「フェルメール光の王国展」が開催されており、仕事帰りに、こちらの方に先に行ってきました
場所は、銀座6丁目のフェルメール・センター銀座。開場時間は、10時から18時までなのですが、木、金、土曜日だけ特別夜間鑑賞会というのがあり、19時から22時まで鑑賞できます。ちなみに、この夜間鑑賞会は、7月22日までです

ここに展示されているフェルメールの全作品37点は、「re-create」といって、最新のデジタルマスタリング技術で、フェルメールが描いた当時の色彩を、原寸大で再現した複製画です



私はフェルメールが好きで、10数年前に、デン・ハーグのマウリッツハイス美術館で「真珠の耳飾りの少女」を観て以来、ヨーロッパの美術館に散在しているフェルメールの作品を見てきましたが、「re-create」とはいえ、彼の作品がずらりと並んだ部屋にいると、何か現実でないような不思議な昂揚感がありました
用意された音声ガイド(小林薫さんと宮沢りえさんが、フェルメールとその娘役で担当)が、1枚1枚、絵の説明をしてくれ、当時の時代背景とかもわかってとてもよかったです
一方、週末、「マウリッツハイス美術館展」に行ってきましたが、大変な混雑で、ただし、個人的に好きなフェルメールやレンブラントの本物の絵画を鑑賞できたという満足感は大きかったです。
銀座の「フェルメール光の王国展」は、会期が延長され、8月26日(日)まで開催されます
ホームページは、 ⇒ こちら
ヨハネス・フェルメール《デルフトの眺望》

[滅紫]
2012年7月 9日 13:16
6月に引き続き澤瀉屋一門の襲名公演が行われている新橋演舞場の7月の話題は何といっても3代目猿之助改め2代目猿翁の舞台復帰だ。6月は襲名口上で登場しただけだったがいよいよ舞台での復帰とあって芝居好きの挨拶は「いつ行くの?」である。平成16年2月(2004年)に病に倒れてから8年と4ヶ月ぶりの舞台。開幕3日目の演舞場に出かけました。


入り口には澤瀉屋の半纏を着た劇場の方が。

場内満員の盛況です。一幕目「将軍江戸を去る」の後は口上、
先月の舞台一杯の勢ぞろいと変わり襲名の3人と成田屋さんのお二人だけというすっきりした口上です。成田屋さんのお二人のユーモアたっぷりのご挨拶に場内大爆笑。
新猿之助さんの「黒塚」が終わるといよいよ「楼門五三桐」「楼門」の場です。浅黄幕が切って落とされると桜満開の南禅寺の楼門、海老蔵さん扮する石川五右衛門の名せりふが終わるとせり上がってきたのは真柴久吉役の猿翁さんです。場内割れんばかりの大拍手!!黒子がついて合引に腰掛けての登場です。超人的な活躍だった元気な猿之助さんを見ている身にはまだまだ不自由そうなお姿には胸が詰まる思いがします。でも舞台でもう一度元気な姿を見ることができるのはやはり嬉しいのひとことです。ついうるうるしてしまいました。まだ完全な回復とはいえない状態で舞台に立つことについては賛否両論があるとは思いますが、お客さまの大多数にとってはやはり嬉しいことだと思います。幕末期に脱疽のため両足切断のあとも舞台に立ち続けたという美貌の女形、三代目沢村田之助の話を思い出しました。幕が閉まっても拍手が止みません。カーテンコールで海老蔵さんと握手、そして現れた黒子は中車さん!舞台上でさらにもう一つの親子のお芝居が進行中だったのです。初日から連日のカーテンコールとか。観客に嬉しそうに手を振っている猿翁さんを見ると役者魂、役者の執念を感じさせられます。話題の舞台へ皆様もどうぞ。
29日千穐楽 お問い合わせはチケットホン松竹:0570-000-489(10:00~18:00)
昼の部はスーパー歌舞伎「ヤマトタケル」です。
[kimitaku]
2012年7月 8日 08:30
いま、勝どき 6丁目
THE TOKYO TOWARS SEATOWAR
新月島運河側 のところで、環状2号線の工事が行われています。
豊洲大橋から、勝どきを通り、終点は隅田川を越えて、新橋方面へ
完成はまだ先の話だそうです。
タワーズマンションから、朝潮小橋に向かう歩道を歩くと、
海側のタワーズマンションにさしかかるところに、 無粋な、鉄柵の壁があります。
ここに、なんとも可愛い。
子供たちの絵が飾られています。
題名は、 「あったらいいなこんな家」
-thumb-150x71-10097.jpg)
-thumb-150x85-10099.jpg)
-thumb-150x88-10101.jpg)
-thumb-150x95-10103.jpg)
-thumb-150x88-10105.jpg)
-thumb-150x84-10107.jpg)
何本かの、プラタナスを挟んで、
ひっそりと、でも、とても 想像力のある、未来を感じさせる、絵画がたくさん。
この殺風景な場所を、明るく彩っています。
-thumb-150x84-10109.jpg)
-thumb-150x92-10111.jpg)
-thumb-150x85-10114.jpg)
工事の騒音を忘れさせてくれますよ。
朝の散歩、昼のひと時、夕方の、街歩きの際にぜひ お立ち寄りください。
子供たちの明るい笑顔が、はずんだ声が聞えてきますよ。

それに、朝潮小橋を渡ると、朝潮運河では、あの震災時に活躍した、
深田サルベージの、
大きなクレーンも望めます。
マンションの10階をはるかに越える大きさです。
散歩の途中 ぜひご覧ください。
[銀造]
2012年7月 5日 08:30
「築地場外あつあつサマーセール」が始まりました。
7月5日から7月31日の期間、「夏の還元セール」として、開催されます。
お得な商品、お値打ち品もあり、お中元、自家消費にお勧めです。
抽選であたる景品 も大変魅力です。詳細は、こちらをご覧下さい。
も大変魅力です。詳細は、こちらをご覧下さい。
http://www.tsukiji.or.jp/modules/info/details.php?bid=249
[滅紫]
2012年7月 4日 13:00
江戸東京博物館の開館20周年企画として特別展「日本橋」-描かれたランドマークの400年ーが開催されている。担当学芸員の方の「見所」解説が主催に入っている朝日新聞にシリーズで掲載されていたのをご覧になった方も多いことでしょう。私も「そのうちに」と思っていたのですがいよいよ会期が7月16日までとなり漸く両国へ。

「描かれた」とあるように日本橋を描いた絵画作品を中心とした資料130点による展示で、日本橋やその周辺を記録する絵や写真類をこれだけの規模で公開するのは初めてとのことです。
第1章「都市・江戸の橋」-都市の中の橋と街道の起点として描いた作品
第2章「日本橋を描くー江戸城、富士山、魚河岸とー」日本橋絵画化上の定番決定
第3章「文明開化と日本橋」明治維新を迎え刻々と変化する日本橋
第4章「石で作られた日本橋」-現在の石造りの橋が架かってからの100年の姿
以上の構成でサプライズ展示として「解体新書」(版元が日本橋にあった須原屋なので)、人力車(日本橋の高札場で営業を開始した)もあります。解説ガイドは何と館長の竹内誠氏ですよ。
広重の「駿河町越後屋」を見ながら「これはまるで宣伝の走り」「白木屋は最初何を商っていたのだったか?」「この川の後ろの橋は一石橋か常盤橋か」(とても観光検定を受けたとは思えない会話!)などと勝手な話で盛り上がりながら展示を楽しみました。江戸好きの友人と一緒にいらっしゃれば楽しみが倍増すること請け合いです。
展示を見ながら日本橋の400年に思いを馳せるのも一興かとオススメいたします。また出光美術館で開催中の「祭ー遊楽・祭礼・名所ー展では「祇園祭礼図屏風」の対照として「江戸名所図屏風」が展示されており寛永年間初めの日本橋の賑わいも見ることができます。こちらは7月22日までです。
江戸東京博物館 7月16日まで 最寄り駅:都営大江戸線「両国駅」A4出口徒歩1分
9:30~17:30 月曜休館























-thumb-150x71-10097.jpg)
-thumb-150x85-10099.jpg)
-thumb-150x88-10101.jpg)
-thumb-150x95-10103.jpg)
-thumb-150x88-10105.jpg)
-thumb-150x84-10107.jpg)
-thumb-150x84-10109.jpg)
-thumb-150x92-10111.jpg)
-thumb-150x85-10114.jpg)