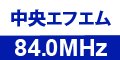[柳 さつき]
2009年10月27日 09:00
江戸時代の初め頃からの歴史をもつ人形町。
江戸歌舞伎の中村座・市村座があったことから、人形浄瑠璃、芝居小屋も集まり、人形師が多く住むようになり、繁栄したそうです。
そんな人形町の人気のイベント「人形市」が、もうすぐ開催されます

開催日程:2009.11.9.(月)~11.11.(水) ※雨天 でも決行です!
でも決行です!
主な会場と内容、イベント予定は・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第一会場:人形町商店街通り
人形や関連商品の展示や販売(約55店)
第二会場:東京穀物商品取引所、1階「東穀ホール」
公演:「辻村ジュサブローの世界」
2回公演(一公演約50分)
第1回 15:00~ 第2回 17:00~ 開演
内容:講演と人形振り付け
出演:辻村ジュサブロー氏
入場無料  注)11.9.(月)のみの公演です。
注)11.9.(月)のみの公演です。
第三会場:人形町大観音寺
人形供養
供養料:人形一体につき¥2000(大きさ、材質などに拘わらず)
組人形は一律¥20000
人形市のお問い合わせ:人形町商店街共同組合事務局さん:03-3666-9044
一週間ほど前の人形町通りは、着々と準備が進んでいました
今年お目見えする「からくり櫓」が楽しみですネ


どうぞ皆さま、お誘い合わせの上、お越しくださいませ!!!
人形町商店街共同組合さんのHP http://www.ningyocho.or.jp/index.html
http://www.ningyocho.or.jp/index.html
[Bird]
2009年10月27日 09:00

人形町の人形美術館「ジュサブロー館」をご紹介します。
「人形町」の名の由来は、江戸時代、この界隈に人形職人が多く住んでいたことから。辻村ジュサブロー氏は、日本を代表する人形作家、そして、人形町の最後の人形職人かもしれません。
美術館、と書きましたが、ちょっと違う...「辻村ワールド」といったらいいでしょうか。一歩中に足を踏み入れたら、もう別世界です。http://www.konishi.co.jp/html/jusaburo/home.html
入ってすぐ、氏が現在取り組んでいらっしゃる「平家物語」の人形たちが迎えてくれます。その人形たち、何とも人間くさい。悲劇の物語の登場人物たちが、酔っ払っていたり、笑っていたり、青ざめていたり。お喋りが聞こえてきそうな魅力的な人形たちです。貝殻が土台の人形もあります。見事な変身ぶりに、きっと貴女は貝殻と気付かないはず。展示室は1階と2階。残念ながら「新八犬伝」の人形たちは展覧会に行っていて留守でしたが、「十勇士」はじめ沢山の人形たちがいます。また1階奥は「目玉座」というスペースで毎月第三火曜日にシャンソンと人形の舞台コンサートが開かれるそうです。勿論、来月の予約をしましたよ!
運がよかったら、辻村氏にお目にかかれるかもしれません。館内は辻村氏のアトリエでもあるのです。作業台には細々とした道具や材料が所狭しと並んでいます。製作途中の作品も見られるかも、です。
そして、私は運がよかった!辻村氏が人形制作のお話を聞かせて下さったのです。辻村先生が歴史の講釈をして下さると、あら不思議、人形たちから「うんうん」と声が聞こえてくるよう。辻村氏の人形が人の心を掴んで離さない魅力があるのは、辻村氏がこうして歴史上の人物を研究し、心を持った人形にして制作しているからなのですね。子供心にも忘れられない思いを刻んだあの「八犬伝」の迫力も、こうして人形に「魂」があったからだったのですね。
ジュサブロー館は「人形町」(日比谷線、浅草線)または「水天宮前」(半蔵門線)から歩いてすぐです。ジュサブロー先生は着流しに銀のピアスの粋ないでたちです。お見逃しなく!
[銀造]
2009年10月23日 09:30
秋の爽やかな日に、神社めぐりで健康的な一日を過ごしませんか。
10月3日に知った「中央区神社めぐり」の事、今日は小伝馬町から月島まで歩きました。
ご朱印帳は各社でお求めできます。1千円です。 ご朱印は各神社で1回200円です。

小伝馬町の駅を上がると、旧跡の説明パネルがありましたが、そちらへは行かず右折。

椙森神社でも「べったら市」の準備万端。こちらも本家、本元とか。
江戸三富の一つで、富籤発行。宝くじの元祖との説明あり。ジャンボくじを持ってお祈りを。

人形町駅交差点付近は、「ええっさ、玄冶店!」跡。 左折して、笠間稲荷神社へ。

笠間稲荷神社。日本三大稲荷の一つとの説明です。

末廣神社。元吉原の守り神。商売繁盛、勝運向上の神様。 奥様からご朱印帳の反対側も使って沢山の神社にお参りして下さいと激励を受けました。

末廣神社のご由緒です。

松島神社。 日曜日の昼過ぎだったので、お出かけ。次回は日曜日以外に来ようっと。
蛎殻町の水天宮。 祈念子孫繁栄。

人形町駅の方から小網神社へ。玉ひでを左にいくと、・・・。

創業明治45年という西洋御料理の小春軒。来た事が無いので味は判りませんが、お値段は、ヴェリー・リーズナブル。 今度、来ようっと。

谷崎潤一郎生誕の地の碑と「幻の羊かん 細雪」の旧看板。誰か商標登録してるの?

人形町1丁目1番地の方向へ進むと、突然鯨が現れました。
鯨と海と人形町の説明を見て、納得。

小網神社。 強運厄除の霊験あらたかなることを祈願して、二礼二拍手一礼。
次は、鉄砲洲神社へ。ちょっと橋めぐりもしましょう。
鎧橋を右に見て、茅場橋を渡り、茅場町の交差点で左折。霊岸橋の途中には日本橋水門、少し前に進んで、新亀島橋をちょっと触って、亀島橋へ。御船手組、将監河岸と河村瑞賢さんの説明パネルがあります。 橋を渡ると、

堀部安兵衛武庸の碑があります。
橋の向こうには、芭蕉の句碑、銀座の柳四世、東洲斎写楽、伊能忠敬さんの説明パネル
亀島橋を戻り、高橋 経由 鉄砲洲神社へ。

今度は、南高橋です。橋の本体には、旧両国橋の一部が使われている「三連トラス橋」

そのまま、真っ直ぐ、信号を渡って30mほどで左側に大きな木の枝葉が目立つ屋敷を見つけましょう。 そこが、 於岩稲荷田宮神社です。

お岩さんは夏の風物詩? お留守で、ご朱印は頂けませんでした。

お百度石の上に玉が。 区民有形民俗文化財です。

近くに、金比羅宮があるというので、立ち寄りました。お賽銭箱の丸金は、少し変わってる。

さあ、中央大橋を渡って、パリへ行きましょう!

橋の中央には、当時の(肩書き無し、個人名の)ジャック・シラク氏のお言葉と銅像が。

パリ広場。フランスのパリに東京広場が建造されたお礼として、平成11年に開設整備。

石川島灯台、住吉神社へ行く前に時間があれば、土曜日なら石川島資料館へどうぞ。

大川端リバーサイドを歩いて、ちょっと足を停めてみましょう。

石川島灯台の下には、元気はつらつの 「緑の風」像。

小橋を渡ると、青銅の鳥居、その奥に住吉神社が鎮座されています。

住吉神社。「海上安全」とご朱印帳にあります。

見過ごしてしまう小さな御社。佃漁業協同組合の銘の入った門柱が。

帰りは、つくだ小橋を渡って帰りましょう。

少し行ったところにあります、佃天台地蔵尊にお参りして。

爽やかな一日。小伝馬町から月島駅まで2時間半でした。 あと、月島を通って、築地の波除神社へ行くと、プラス1時間。 大体3時間半から4時間で楽しく、ご利益と健康が得られるでしょう。 是非、中央区神社めぐりをお楽しみ下さい。 銀造でした。
[柳 さつき]
2009年10月22日 09:00
10月15日(木)、快晴
たまたま新川の叔母を訪ね、住んでおりますマンションにおりましたら、雅楽特有の三管三鼓=笙:しょう(プロでポピュラーなのが東儀秀樹さんですね!といえばご想像がつきやすい でしょうか?)や篳篥:ひちぎり、龍笛:りゅうてき=の雅な音色が聞こえてきました。
でしょうか?)や篳篥:ひちぎり、龍笛:りゅうてき=の雅な音色が聞こえてきました。
隣接する新川大神宮を窓から覗き込みましたら、宮司さんや黒い礼服の方々による例祭が厳かに取り行われていました。
招待状かなにかをお持ちの方が受付をしてご出席なさっているので、これは近くには行けないなぁと・・・・・・・・・。失礼ながら、その様子を上(マンションの窓)から撮らせていただきました 新川大神宮の神様、どうぞお許しくださいますように。
新川大神宮の神様、どうぞお許しくださいますように。
 これからご祈祷が始まります。
これからご祈祷が始まります。


ご列席の方々のお名前が呼ばれ、順にご参拝し、お札を授与されていらっしゃいました。
その後、夕刻に新川大神宮に参拝しながら、少し境内を拝見させていただきました。


新川といえば、江戸時代、現在の新川大神宮の前に東西に流れる運河があり、両岸には酒蔵が立ち並んでいたそうです。
その開墾に当たったのが、新川一丁目にお屋敷があった豪商:河村瑞賢だそうです。
関西の酒造元から樽詰めされ水路で運ばれて来たお酒は「下り酒」と呼び、蔵の入り口にはちょいと一杯できるところがあったり、秋には新酒を一番早く運ぶ船の競争に、江戸っ子は大喜びだったそうです。
江戸時代の新川河岸に行きたいですね~っ!!


道理で、境内の寄進者の札に、私でも知っている全国の有名な酒造会社さんや醤油製造会社さんのそうそたるお名前が並んでいたのですね


例祭では、直会:なおらいで「新川締め」をし・・・・・「ヨイヨイヨイコラ、ヨイゴハンジョー」と掛け声と手拍子をし、なみなみとお酒の注がれた大盃を飲み干すのだそうです。
 耳寄り情報
耳寄り情報 そういえば、叔母から聞きましたところ、この新川大神宮のはす向かいの酒問屋「加島屋」さんの会長さんが宮総代を勤めていらっしゃるそうで、「加島屋」さんオリジナルの清酒「惣花」は宮内庁御用達だそうです。恥ずかしながら、初めてお聞きする銘柄だったのですが、同じ新川一丁目の「今田商店」さんで扱っていらっしゃるそうです。
そういえば、叔母から聞きましたところ、この新川大神宮のはす向かいの酒問屋「加島屋」さんの会長さんが宮総代を勤めていらっしゃるそうで、「加島屋」さんオリジナルの清酒「惣花」は宮内庁御用達だそうです。恥ずかしながら、初めてお聞きする銘柄だったのですが、同じ新川一丁目の「今田商店」さんで扱っていらっしゃるそうです。
「加島屋」さんや「今田商店」さんのHPは見あたりませんでしたが、「今田商店」さんでは「酒屋寄席」を催していらっしゃるんですね!今年の酒屋寄席に行かれた方のブログをご紹介させていただきました。http://tsutomu3.com/09year/0330sakayayose/yose.html
[海舟]
2009年10月21日 10:00
明和8年(1771年)3月、千住小塚原の刑場で、罪人の腑分け(解剖)
に立ち会った前野良沢、杉田玄白、中川淳庵の3人は驚きの念を隠しきれ
ませんでした。
腑分けされた死体の組成が、持参した『ターヘル・アナトミア』
の記述とおりだったからです。
翌日、鉄砲州にある豊前中津藩中屋敷内の前野良沢邸に参集した3人
はこの蘭書を翻訳することを決意します。
多くの同士の協力を得て3年余りの歳月を費やし安永3年(1774年)、
『解体新書』として訳出、完成させました。
公刊に当たっての著作者は越前小浜藩医師・杉田玄白、同・中川淳庵、
一橋家侍医・石川玄常、幕府侍医・桂川甫周の4人でした。彼等の盟主で
あり訳出の主力であった前野良沢の名がありません。一説には不完全な
翻訳の故に、前野良沢は公開することを快しとせず名を連ねることを固辞
した為といわれています。
桂川甫周の父・法眼・3代甫三国訓は杉田玄白とは旧知の仲であり、
また奥医師としての政治的な立場を介して『解体新書』発禁に対する配慮
を策したと思われます。桂川家は初代・甫筑邦教、2代・甫筑邦華を経て
既に侍医として公家そして奥向きにも大きな信頼を勝ち得ていました。
『解体新書』出版に際し、オランダ通詞・吉雄幸左衛門耕牛が序文を寄せ、
秋田蘭画の開拓者・小野田直武が解剖図を描きました。
『蘭学事始』は杉田玄白が83歳の時、約半世紀に亘る蘭学界の概況、
『ターヘル・アナトミア』訳出に際しての苦労談、蘭学界周辺の人びとの
人物評などを書き記した回顧録です。
『ターヘル・アナトミア』訳出より84年後の安政5年(1858年)、大阪・
適塾塾頭であった中津藩藩士・福沢諭吉が藩命により、同地に蘭学の
私塾を開設することになります。
『蘭学事始の地』は平成20年(2008年)に創立150周年を迎えた近代
日本最古の私立学校『慶應義塾発祥の地』でもあります。
参考図書 : 全訳注 片桐一男『杉田玄白 蘭学事始』
講談社学術文庫

[shikichan]
2009年10月21日 09:00



(写真上) 1933年(昭和8年) 髙島屋東京店オープン 今年6月重要文化財に指定される。
「西洋の歴史様式に日本的な要素を加味した」当初設計部分と「近代建築の手法を駆使
した」増築部分からなりたっており、その全体が一体不可分の建築作品として完成度が
高くわが国の百貨店建築を代表するものの一つとして重要である。と、評されている。
(写真中) 1933年(昭和8年) 屋上に七福殿を建立。人間が願い求めるすべての福を収め
ており、一周するとご利益があると言われている。福禄寿、毘沙門天,布袋尊、弁財天
大黒天、寿老神、恵比寿神が祀られている。中は非公開。
(写真下) 1950年(昭和25年) タイ国より一歳半の小象を貰い受ける。下関まで船で
運び、トラックで搬送。銀座通りの正面玄関より クレーンで屋上まで運び上げた。
小象"高子"はお子様を背中に乗せ大いに喜んでもらった。昭和29年には惜しまれて
上野動物園に行き、その後多摩動物公園で余生を送った。屋上には高子チャンがいた
モチーフが残っている。
![]()

![]() でも決行です!
でも決行です!![]() 注)11.9.(月)のみの公演です。
注)11.9.(月)のみの公演です。![]()
![]()


![]() http://www.ningyocho.or.jp/index.html
http://www.ningyocho.or.jp/index.html






























 これからご祈祷が始まります。
これからご祈祷が始まります。