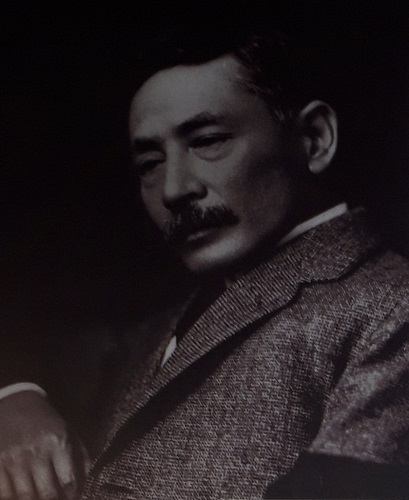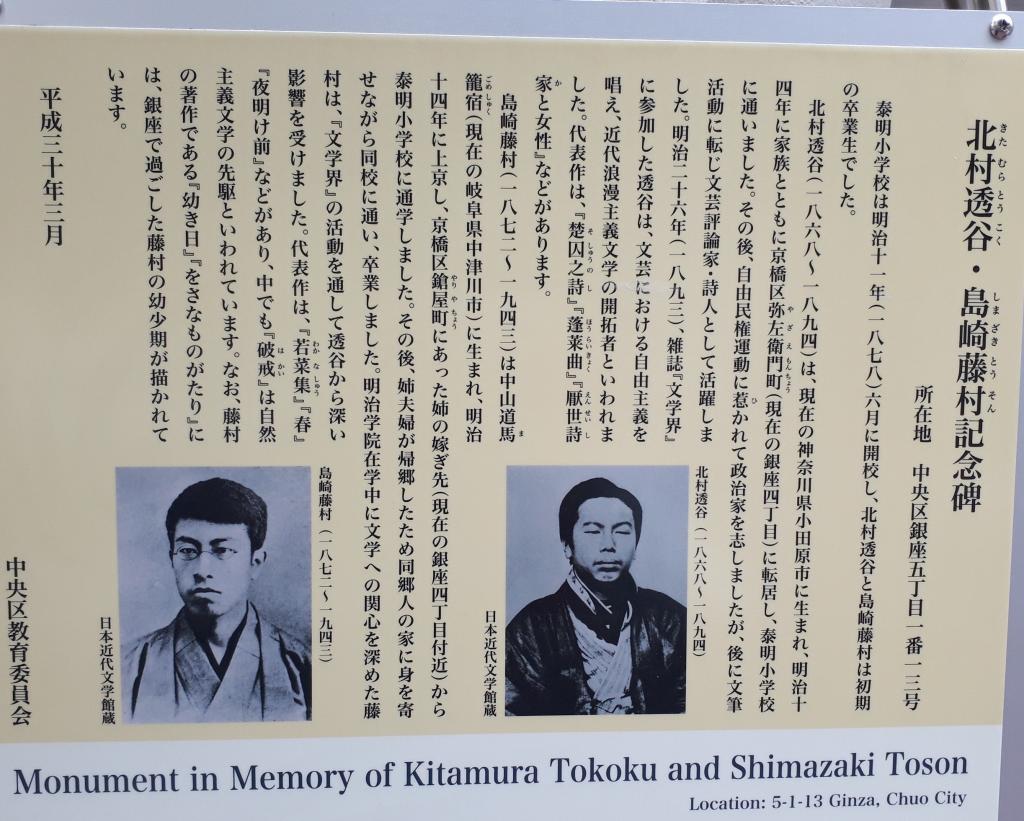にゃんボク プロフィール
-

寿司をめぐるあれこれ
(ワタクシ事で恐縮ですが、今をさかのぼることウン十年・・・・)<写真は矢の根寿司HPより>私が小学校2年生の夏休みに、アメリカから当時中学生のJ君が我が家にホームステイに来ることになりました。今と違って外国人がまだ珍しく、ましてやアメリカ人となるとそれだけでサインを求めるような風潮もまだ残っていたように思います。J君と歩いていると、なんだか自分の価値が高められるようなくすぐったいような感覚。「そうなんだよ、アメリカからJ君がうちに来てるんだよ」。 その年の夏休みは私にとって、何もかもが特別なものとなりました。(自分の家がある)埼玉から移動して東京のビル群を見上げ、初めて新幹線に乗って初めて京都や鳥取に行き、おいしくない緑茶のボトルを新幹線で飲み(うげぇと顔をしかめる味だった)、砂丘ではラクダにもまたがり、と。日本には無い甘さのアメリカ土産のチューインガムを食べ、だれでも膨らませられると言われた風船ガムがうまく膨らまない悔しさを味わい、そして毎日晴れていたとの記憶の中で、真っ黒になるまでJ君たちとプールに行っていたように思います。そんな夢のような夏休みも終わりを迎え、J君を家族や親せきで送別する時がやってきました。8月も末になると夜は少し肌寒いような時代でした。虫の音と相まってもの悲しさがつのります。 最後の晩餐は、ごちそうでのおもてなしでした。母が言った「今日はお寿司の出前(もある)よ」に対して、私は確かに「寿司なんか食べたくない」といった趣旨のことを言いました。子供心に、「せっかくのご馳走になんてことを言うんだ」と自ら思うとともに、「(別れが悲しく)寿司を食べて喜ぶ心境じゃないんだ」との感情が交錯し、寿司の味はわからず、少し涙のしょっぱさが残るような食事をした記憶が残っています。 なぜこんな(ポエムのように)出来事を鮮明に覚えているのか。なぜ、この記憶は小学校2年生であって、3年生ではないと明確に言えるのだろうか。 批評家の東浩紀氏が、こう書いているのを読みました。「大人の世界は”反復可能性”に満ちている。皆が、今回だめならば別の機会にとの発想で生きている。夏に休暇が取れなければ冬に休暇を取ればいいし、今年は海に行けなければ来年行けばよい。(中略)ところが子供相手にはその欺瞞が暴かれる。小学三年生の休暇と小学四年生の休暇は違う。幼馴染は作り直せないし、中学の入学式は一度しかない・・・」 そうか、と私は思いました。人生は短い。そして本来は取り返しがつかない。しかし、心の健康のためにも処世術のためにもそのことを普段は忘れている。大人になってからの私たちは「あれはいつのことだったっけ?3年前か4年前からすら思い出せない」となる。 ところが、である。これを一変させたのが2020年。世界は新型コロナ禍に覆われました。これは反復可能性を奪う出来事でした。2020年の前と後では気を付けるポイントが違う。生活様式が違う。大人ですらそうなのですから、子供にとってはどれだけの大事でしょう。 コロナ禍の中で完全に在宅勤務となり、外食は極力控えるようになりました。そんな中で、テイクアウト、いや昔からの(板前さんが届けてくださる)出前を取るようなったのが、日本橋室町に構える「矢の根寿司 日本橋本店」。 出前で寿司を取る、は、もしかしたら子供のころ以来かもしれない(だいたい現地で食べる)。ある意味私にとって特別だった出前スタイルが、2020年を経て推奨されるべく日常的な様式へと一気に変わりました。暖簾をくぐるのに必要な心構えも出前なら不要です。 向田邦子さんは「どんなに好きなものでも気持ちが晴れていなければおいしくない。反対に多少気分がふさいでいてもおいしいものはやっぱりおいしい。どちらにしても食べ物の味と人生の味とふたつの味わいがある」といった趣旨のことを書かれています。 矢の根寿司の寿司はだいたい私が最初に箸を伸ばす”ねぎとろ”の1巻目からうまい。忙しくても気分がふさぎがちであっても、いつ食べても最後まで旨い、と私は思うのです。
グルメ情報その他日本橋・京橋周辺にゃんボク
記事を読む
-

あるエッセイと日本橋のデパート
一時期、仕事の関係で石川県金沢市を訪れる機会が多くありました。 かつては金沢への移動と言えば、飛行機とバスを乗り継いでいったものが、北陸新幹線が開通してからは新幹線がメインとなり、東京発で始発に乗ると、9時半頃からの金沢での打合せに間に合う(間に合ってしまう)ようになり、金沢への出張がほぼ日帰りで完結することになりました。金沢も旅情を感じながら移動していく場所ではなく、効率的にビジネスを行える都市の一つになったと感じられ、移動自体の便利さと引き換えに、ちょっとしたものが失われたような気分を味わいました。 その北陸新幹線では車内誌「トランヴェール」が各席に配置されており、(不朽の名作『深夜特急』の著者)沢木耕太郎さんのエッセイ「旅のつばくろ」の連載もありました。新幹線に乗るたびに読んでいたなかで、ある日のエッセイが印象に残りました。 その内容はおおむね、こんな流れでした。 ”(沢木さんは)日本橋のあるデパートで繁忙期に「特選品」(高級品売り場)のアルバイトを4年続けていた。その売り場では大物政治家の家族や大会社の社長夫人などの顧客が担当の店員を引き連れ、あれ、これと指をさしながら買い物をしていく。買ったものを顧客は自分で持って帰らず、担当の店員がタクシーでお届けに上がる。お届けに上がると、「上流階級」といってもアルバイト学生の接し方には雲泥の差があることを知る。ある夏、その顧客でもある「上流階級」の息子がふとしたきっかけで同じアルバイトに入ることになり、接点を持つことになるのだが、バイトの最終日にその彼から「軽井沢の別荘に一緒に行かないか」と誘われた。(沢木さんは)悩みながらも予定があったため断わることになる。彼は「またの機会に」といったものの、その「またの機会」は無かった。彼がアルバイトに来たのはそのシーズンだけだったからだ。” ”長い年月を経て軽井沢に(沢木さんが)降り立った際、静寂に包まれる軽井沢の別荘地にて、不思議な感覚に包まれることになった。かつて彼が誘ってきた別荘はここと地続きのはず。もし、あの時の彼の誘いを受けていたら・・・その世界に深く足を踏み入れていたら「ありえたかもしれない別の人生」があったかもしれない。誘いに乗っていたら、逆に「今の私が手に入れている世界は持ちえなかったはず」・・・” といった内容でした。 なぜ、このエッセイが私にとって印象深かったのか。 このエッセイを読んだ時よりも少し前、私が約5年間の大阪勤務から東京に戻り、ある日、日本橋の三越本店の天女像の前に立った時、ちょうどパイプオルガンが優雅な音を奏で荘厳な雰囲気がいよいよ増すのを感じました。その時、私は音と空間から不思議な感覚に包まれるとともに、「あぁ、東京(中央区)に戻ってきたのだな」とここで感じ入ることになります。既に東京に戻って日数が経過していたのに、ここで、この場所で、”戻ってきた”との感覚に包まれたのです。 他の都市に転勤したが故に、少し背筋が伸びるような特別な場所が貴重になっていることを感じ、それを東京と結び付けて意識することになったこと。また、ふとしたきっかけ(偶発的なこと)での転勤が(沢木さんのエッセイで言うところの)「ありえたかもしれない別の人生」の側を歩んだのではないか?との思いに捉われたこと。 (エッセイでの舞台がたまたま同じ日本橋のデパートだったことも、印象深さにつながったのは言うまでもありません。) 昨日(2月23日)、日本橋三越の天女像の前に立ち、そのことを思い出しました。今は不思議な感覚に包まれることは無くなってしまいました。でも、特別な場所であるとの思いはむしろ強まっているような気がしています。
中央区百景歴史・文化その他日本橋・京橋周辺にゃんボク
記事を読む
 オフィシャル
オフィシャル